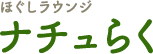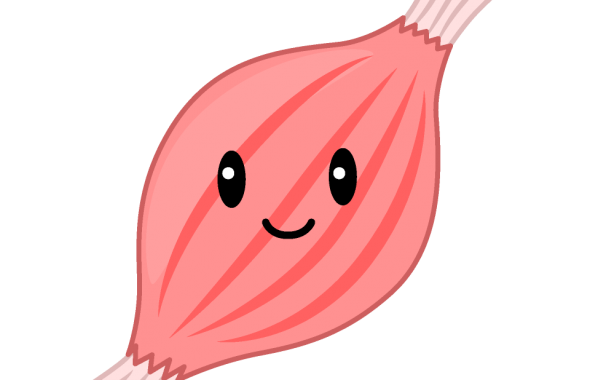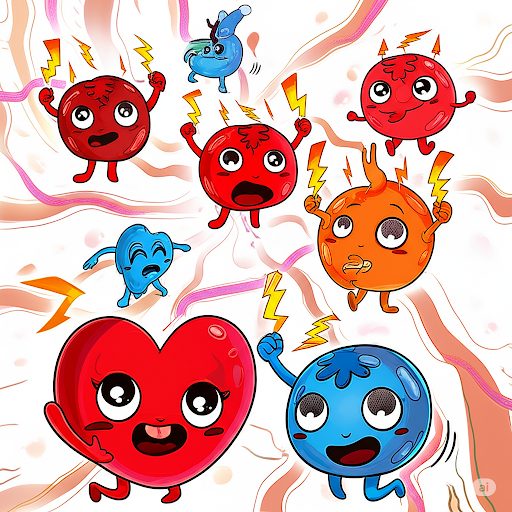
季節の変わり目に体調が崩れやすい理由
自律神経の乱れ:司令塔の混乱
私たちの体には、意識的にコントロールできない生命維持機能(
季節の変わり目は、
- 急激な環境変化への対応: 気温、気圧、湿度の急激な変化は、
体にとって大きなストレスとなります。 体はこれらの変化に対応しようと、 自律神経をフル稼働させますが、 その変化のスピードが速すぎたり、変動幅が大きすぎたりすると、 神経系が疲弊し、バランスを崩してしまうのです。 - 体温調節機能の過負荷: 例えば、春先は暖かい日と寒い日が繰り返され、
体は頻繁に体温を上げたり下げたりする必要があります。 この体温調節を担うのも自律神経の重要な役割であり、 激しい気温の変化は自律神経に大きな負担をかけます。 - 気圧変動の影響: 気圧が急激に変化すると、
私たちの血管は収縮したり拡張したりします。 これは血管運動神経という自律神経の一部がコントロールしていま すが、急な気圧の変化に血管がうまく対応できず、頭痛やめまい、 倦怠感といった症状が現れることがあります。 特に低気圧が近づくと、副交感神経が優位になりやすく、 血管が拡張し、 神経を圧迫することで痛みが生じると考えられています。
ホルモンバランスの変動:体のリズムの狂い
季節の変化は、
- 日照時間とセロトニン・メラトニン: 日照時間は、
気分を安定させる神経伝達物質であるセロトニンの分泌を促し、 睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑制します。 季節が変わり、日照時間が大きく変化すると、 これらのホルモンの分泌リズムが乱れ、 気分の落ち込みや睡眠障害を引き起こすことがあります。特に、 秋から冬にかけて日照時間が短くなる時期は、季節性情動障害( 冬季うつ病)を発症する人もいます。 - ストレスとコルチゾール: 環境の変化によるストレスは、
ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を促します。 一時的なコルチゾールの増加は、 体が変化に対応するために必要な反応ですが、 慢性的なストレス状態が続くと、 コルチゾールの分泌が過剰になり、 免疫力の低下や自律神経の乱れにつながることがあります。
免疫力の低下:防御システムの脆弱化
自律神経の乱れやホルモンバランスの変動は、
- リンパ球の機能低下: ストレスや睡眠不足は、
免疫細胞であるリンパ球の働きを低下させることが知られています 。季節の変わり目は、 環境の変化によるストレスや睡眠不足が起こりやすいため、 免疫力が低下し、風邪や感染症にかかりやすくなります。 - 粘膜の防御機能の低下: 乾燥した空気は、鼻や喉の粘膜を乾燥させ、
異物の侵入を防ぐバリア機能を低下させます。季節の変わり目は、 空気が乾燥しやすいため、 ウイルスや細菌に感染しやすくなります。
アレルギー反応の活発化:過剰な免疫反応
特定の季節は、アレルギーの原因となる物質(花粉、カビ、
- 花粉症: 春先のスギやヒノキ、秋のブタクサなどの花粉は、鼻水、
鼻詰まり、くしゃみ、 目のかゆみなどのアレルギー症状を引き起こします。 - アレルギー性鼻炎・喘息: 温度や湿度の変化、ハウスダストやダニの増加なども、
アレルギー性鼻炎や喘息の症状を悪化させる要因となります。
このように、季節の変わり目には、自律神経の乱れ、
ご自身の体調の変化に注意し、
当サロン「ほぐしラウンジ ナチュらく」では、オールハンドによる全身施術。施術歴12年の経験から各技法の良いところを組み合わせた独自の手技を研究し習得。さらには各技法をより効果的に発揮できる揉み方も研究・開発。基本の施術だけでなくこれらを総合的に取り入れた施術をする事でエリアトップクラスの高いレベルの施術の提供を行っています。この研究・開発した施術の中には筋膜マッサージ(筋膜リリース)やオイルリンパ(リンパドレナージュ)など、多数の理論・技術を取り入れた施術も含まれています。また、